種の使命
遠いどこかに置かれたサーバー群(クラウド)に接続して使用した料金を支払う義務を相互に課している人類とは異なり、草には雲に雨の料金を支払う義務がない。自然経済は実際にそれを使って新しい「自分たち」を構築するための炭素や水素など92種類の宇宙元素1を使って取引を行なっている。自然は、食べることのできない紙や金属やデータを介在させずに、再生的な直接交換システムを採用している。自然経済の市場では、参加者の多様性により物質循環が高まり、参加者全員が繁栄するように、つまり生態系が活性化するように設計されている。

「エネルギー、仕事、種、多様性」と生命の存在理由
ヒトは日光浴で生きていくことはできないが、植物はできる。植物は恒星太陽から届く不規則で無秩序なエントロピー的放射エネルギーを、発散性の放射エネルギーの角度を再配置することで、反エントロピー的な分子構造が規則的で秩序付けられたパターンへと、つまり炭化水素分子に変換する。もし植物が光合成できなければ、植物自身が成長できず、炭素循環がなくなり、炭素を含む物質である有機物はほとんど存在しなくなる。
我々生命体は単なる寄せ集めではない有機体であるが、それは時間を含む幾何学パターンとして秩序を持っていることに由来する。美しい分子構造の多面体的特徴が途方もない連続スケールの旅を経て、我々を形作る。対称性やフラクタル性などの宇宙的デザインルールが我々にも適用されている。
植物は宇宙に向かって成長していく。宇宙に向かって葉を広げ、宇宙からの光を受けて生命の源を生み出す。生命を養う重要な使命を帯びている。植物から供給される炭素化合物は別の植物が自らを組み立てるための素材となる。動物や菌類も同様に恒星エネルギーを物質化した素材で自らを組み立てている。そして、絶えず届けられるエントロピー的エネルギーは惑星地球の表面で生命体の分子構造による整頓する仕事によって生態系の多様性へと変換されていくことになる。仕事をすればするほどエネルギーは増え、仕事も増える。増えた仕事を生態系内で分担する。分担できない仕事が残る。誰かが対応できるように進化する。種が増え、多様性が増強される。この繰り返しで、エネルギーが増え、仕事が増え、種が増え、多様性が増えていく。多様性が拡大していく限り、生命の仕事は増えていく。惑星地球全体が繁栄することを意味する。エネルギー、仕事、種、多様性の相互関係�がエントロピー増大則によって地球の繁栄につながるのである。生命の仕事はすなわち生命の存在理由でもある。
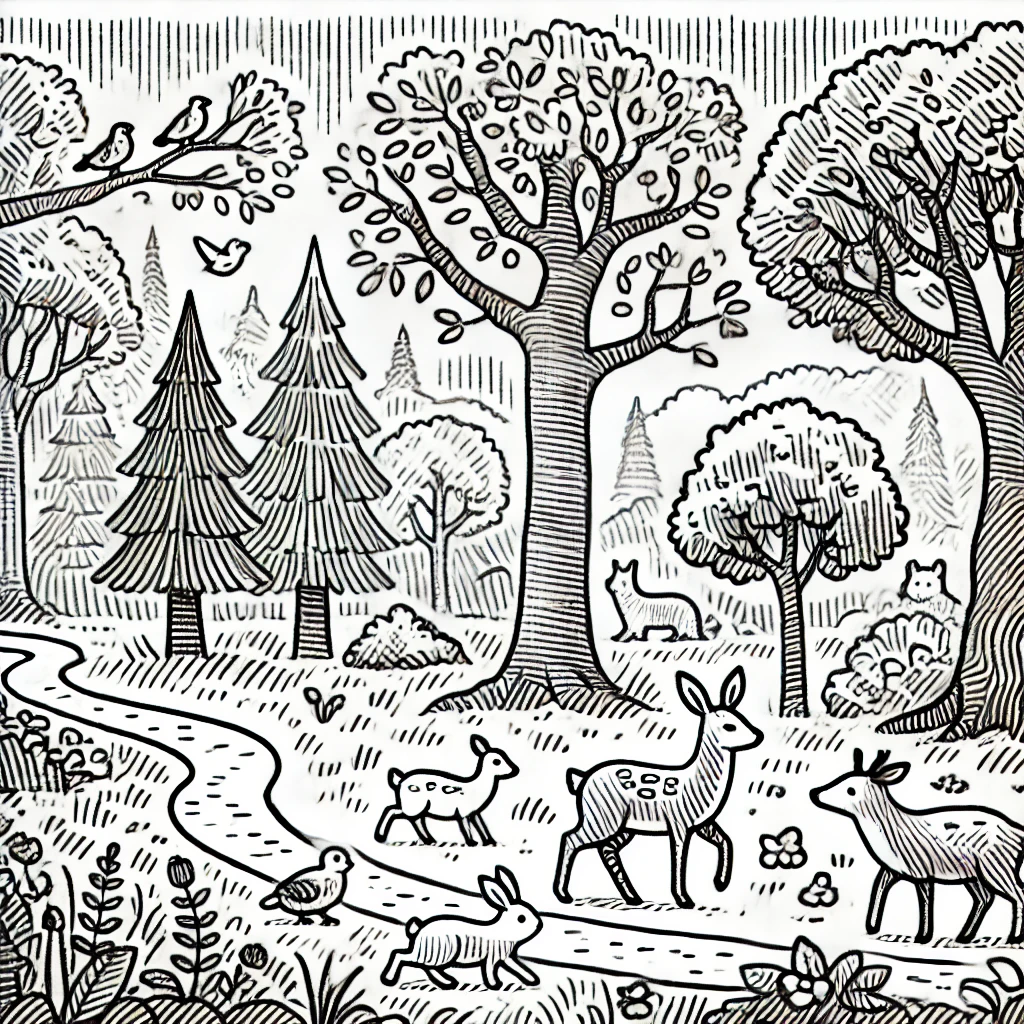
生理最適は生態最適に斥力として働く
例えば、単一種類の生物を大規模に育てるという現在の農業の方向性は、この自然の物理的な繁栄の仕組みに反している。それが植物であれ動物であれ、単一のものを大規模に増やして消費していくやり方は地球表面で起きている調和的で必要十分なエネルギー循環を損なってしまうことになる。エネルギーを物質に変換し、物質を生命体に変換し、生命体を生態系に変換し、生態系を恒星系のエネルギー循環システムに変換する一連の連環構造を破壊してしまうのである。
農業は、ヒトが生きていくために必要なエネルギーを得るための方法である。だとすると、農業を営むことが「単一の作物を大規模に育てること」を意味する現在の人類の認識は宇宙的に矛盾していることになる。黄金の卵を産むガチョウのように、放っておいても自然にエネルギーが得られる循環システムを自分たちの手で壊すことにつながるからである。エネルギーを得るためにしていることが、地球に降り注ぐ恒星エネルギーの大部分を捨てるために役立っている。非現実的だと大笑いされるかもしれないが、現在のやり方な�らば、農業をやめるほうが地球上のエネルギーは増えるかもしれないのである。それは私たち人類の食糧を増やすことを必ずしも意味しない。しかし、やり方によっては、食糧の問題を解決することができる。超自然的なやり方2をすればいいのである。
恒星の放射エネルギーとそれを全生物が利用可能な物質に変換する植物、有機物から無機物に分解して再利用可能にする菌類、遺伝子を媒介して進化をもたらすウィルス、植物を食べ、菌類を飼い、ウィルスを運ぶ動物。全生物が相互相補的に役割を果たすことで多様性が増強され、生態系全体が拡張されていく。拡張された生態系のサービスによってどんな生き物にもエネルギーが行き渡り、宇宙の居場所が確保される。「単一のものを大規模に」の結末は最終的には生物の一種にすぎないヒトの居場所を奪うことにつながる。特定の限られた一種の繁栄を目指す生理最適は生態最適に対して斥力として働く。
二次産業化される一次産業
農業や漁業や畜産業などの一次産業は、自然生態系が生み出す零次産業3の余剰分のエネルギーに依存している。古代の人々は自分たちが生きていくために必要な食糧を再現性のある形で生み出す業を編み出した。資源や燃料はほとんどの場合、自然が与えてくれる植物と動物であり、自然生態系の再生能力を超えないところでそれぞれの仕事──ほとんどが一次産業の仕事──を営んでいた。
工業は二次産業であり、零次産業から一次産業までの余剰分のエネルギーに依存する構造になっている。惑星地球で使えるエネルギーは、恒星太陽の放射エネルギーに全面的に依存している。人類が出現する遥か昔に、豊かな生態系によって零次産業の副産物は大量に地球内部に蓄えられた。埋蔵金の如く地中深くから掘り起こして使っている化石燃料は、過去の地球の自然生態系のエネルギー循環構造によって利用可能な物質として貯蔵されていたものである。地球の内部に蓄積していたエネルギー貯金を使って機械を動かし工場を稼働させることで工業は成立している。
そこで働く人のエネルギーは一次産業によって供給されている。しかし、その一次産業は科学技術の発展により、現代では工業化が進んでいる。つまり、二次産業として捉えたほうがわかりやすいほど、化学分子的に最適化されている。現代農業の最先端部分では、生命に欠かせない「土」を必要とせず、工場によって生産される工業製品となったものもある。本来の生態とは程遠い生育環境で育てられた生き物、というよりも人工的に作られた(中には文字通り「編集」された)食べ物が大量に生産され、世界中の食卓を目がけて供給されている。そのことが自然の生態系に多くの、そして大きな副作用を引き起こすことになっている。
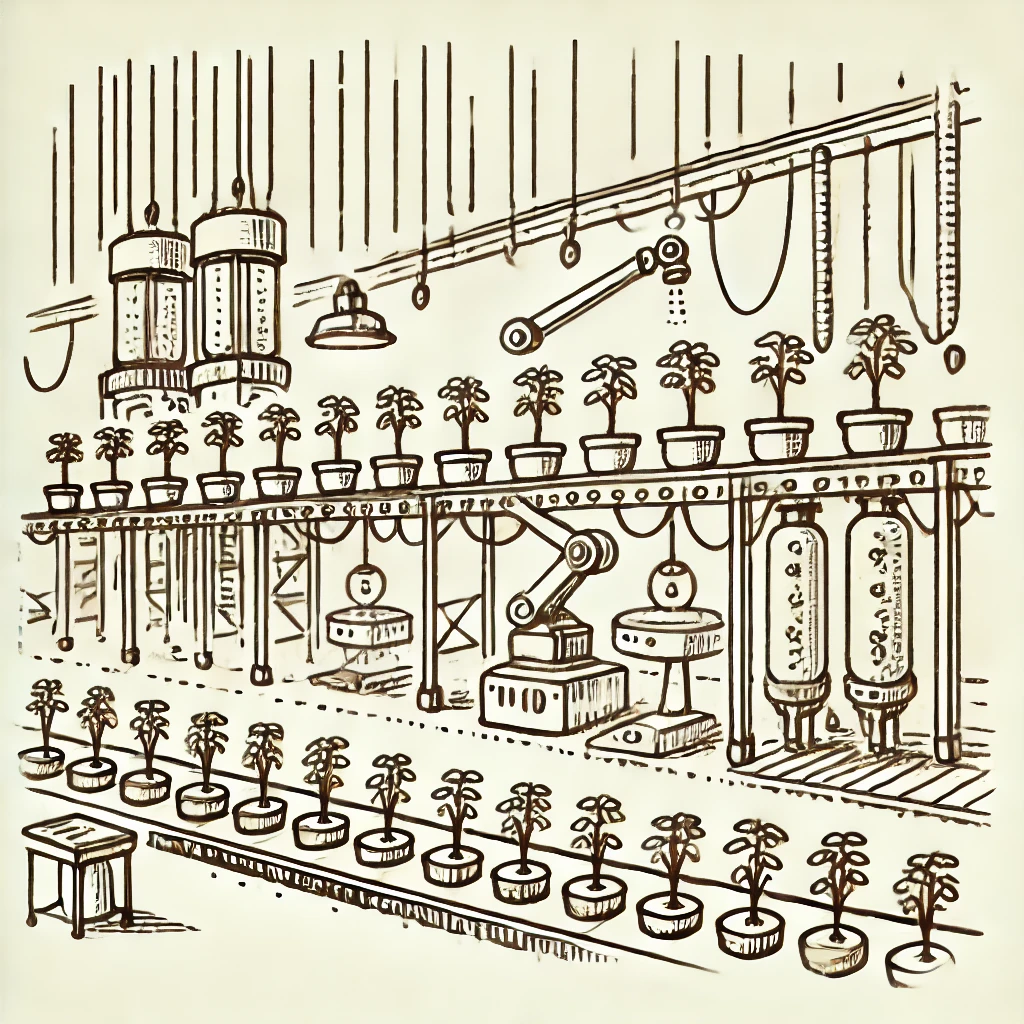
それぞれの「持続可能(sustainable)」
もしも、化石燃料が食用に適するものだったら、直接食べたほうが良いかもしれないくらい、二次産業化された一次産業はエネルギー効率が悪い。自然の生態系から糧を得るだけだった頃の一次産業とは異なり、持続可能なやり方ではない。では、「どんな状態が持続可能(sustainable)なのか」ということを世界中で大急ぎで考え始めている4が、この記事のように、それぞれの観点で、それぞれ勝手な解釈を述べている。「電気自動車に乗り換えよう」とか、「増えすぎた二酸化炭素を吸い取る技術を発明しよう」とか、「太陽光発電パネルをあちこちに敷き詰めよう」とか、新技術によって「持続可能な状態」を目指すものもあれば、「牛にゲップさせるな」とか、「セレブはプライベートジェットに乗るな」とか生き物の習性を糾弾するものもある。他にも、「丈夫で手がかからない遺伝子組み換え作物を普及させよう」とか、「水田はメタンを発生させるから稲作をやめろ」とか、「AI管理の植物工場は無農薬で環境に優しい」とか、農業のやり方を変えようとするものもある。「エコバッグを持参しよう」とか、「ストローは紙にしよう」とか、挙げればキリがないほど、みんなそれぞれの「持続可能な状�態」を考えている。
我々ポリマスリサーチの考えもそのひとつにすぎないが、「私たち人類が持続可能、かつ、私たち以外の全生物が持続可能、かつ、文明社会が持続可能、かつ、地球環境を恒久的に復元可能」という条件を満たすものはそれほどない。「ひとりの個人、あるいは、ひとつの会社、あるいは、ひとつの産業が持続可能」という条件は含まれないから、ほとんどがそこで脱落してしまう。
植物や動物を機械的に早く大きくするために、化石燃料が大量に使われ、反自然的に作用する人工的な化学物質が流通する。自然の生態系が調和によって果たしていた仕事を、人類だけで果たそうと努力した成果が地球規模の気候変動として現れている。自然の力を借りずに、ヒトの知恵だけで何もかも生み出せると思い込んだツケの返済期日が到来している。何でも分子生物学的に解析して化学的に再現すれば、魔法のように欲しい結果が得られると──催眠術にでもかかっているかのように──私たち人類はまだ強固に信じ込んでいる。その結果、土は作るものになり、海は作るものになり、食べ物は作るものになった。植物でも動物でも、欲しいものは何でも自分で作り出せるものであるかのように、私たち人類は過去最高の傍若無人さで自然を扱っている。自らの「知性」に陶酔している。
生態系が育つ手助けをする
私たち人類は、心ここに在らずである。過去�の自然生態系サービスの副産物を使うことに夢中になり、現在の自然生態系が与えてくれる恩恵は見えていない。街を行進するゴジラのように、足元の生態系をことごとく破壊してしまっている。
大地の球体である地球にとって、土は生命の源である。多くの生き物が死に、分解され、そして新しい命となる場所である。海の助けを借りながら、雨が降り、風が吹き、夏には太陽の光が燦々と降り注ぎ、冬には雪が降り積もる土の上で私たちは自然の一部として育っていく。
私たちには、土に、海に、自然に存在する私たちを生かすものすべてに料金を支払う義務がない。ただ感謝を捧げるばかりで、何の恩返しもできていない。最も大事なことは、心を尽くすことである。自然に対して心を尽くすとは、生態系を生み出し、拡張するということであると思う。壊してしまった生態系を復元することも含めて、生態系が育つ手助けをするということが全生命の一部として、全生物の代表として、私たち人類にできる唯一の貢献であると捉えている。

多くの生き物とともに私たち自身も育つ
畑を耕す。この一万年以上に渡る習慣は土壌中の地下生態系をことごとく壊してきた。土壌微生物たちの多くの犠牲とともに、人類は飢饉や疫病を経験してきた。目に見えない地中変動の災厄を医学的に抑え込んできた私たち人類は、目に見える気候変動に対してどのように対応するのだろうか。科学が偶然、「土壌中に」土壌細菌が産出するペニシリンを発見して恐ろしい病を特効薬で克服したように、「大気中に」恐ろしい異常気象の特効薬を見つけるのだろうか。そんなミラクルなセレンディピティに地球が46億年を掛けて大事に育ててきた全生物の未来を掛けていいのだろうか。あまりに愚かすぎやしないだろうか。
「畑耕すの恥だが役に立つ」の時代はそろそろ終わらなければいけない。常識のアップデート周期はわからないが、新しい常識によって自然に対する認識を改めれば、「畑耕さないの自然だし役に立つ」の世界はもうすぐそこまで来ている。
私たちを含む自然生態系が育つ手助けをするということは、他の多くの生き物とともに私たち自身が育つ手助けをすることにもなる。そういう考えで、我々ポリマスリサーチは、単一作物ではなく生態系が育つファーム「生態系ファーム」を地球各地に増やしていくプロジェクトを進めていく所存です。
ご意見ご感想はお気軽に。協力者はいつでもウェルカムです。

